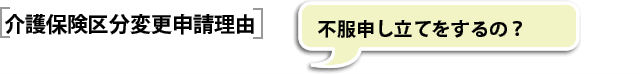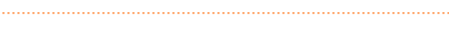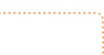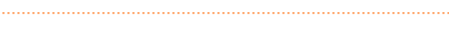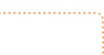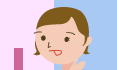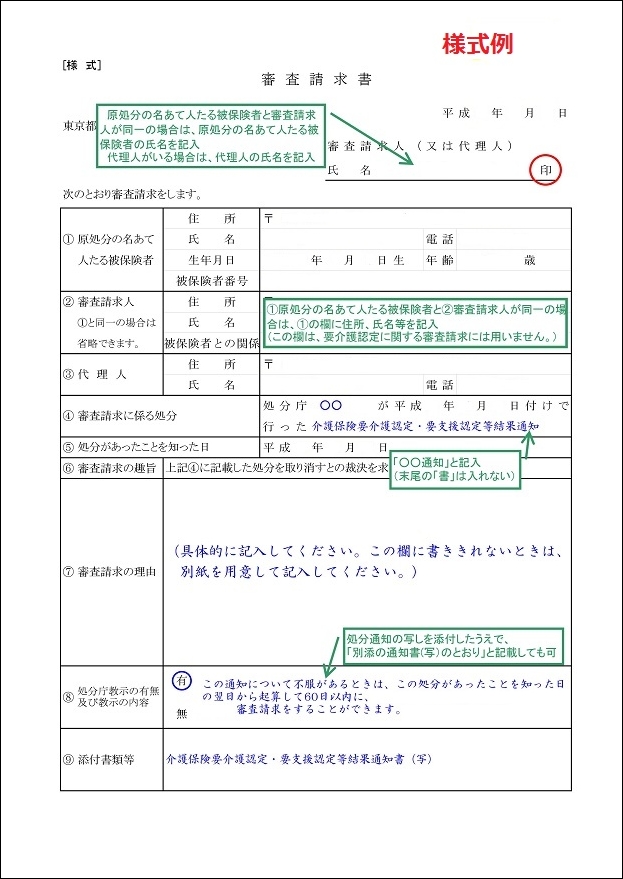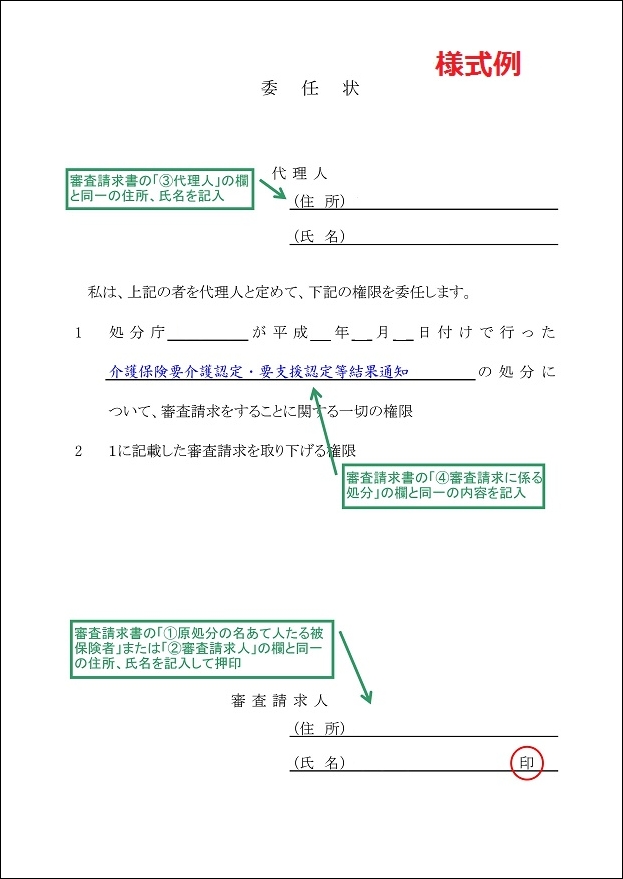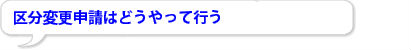介護保険区分変更とは
そもそも介護認定は、どの様に決定されるのかご存知ですか?
1次判定の認定の判断と結果
以上を国のデータベースされた膨大な事例が入力されたソフトと照合され判定と結果がまずは出されます。
その結果
- 自分で出来る
- 人の支えが必要
- 人の一部介助が必要
- 自分で出来ない
以上の様な大まかな判断結果となります。厚生労働省の定めた基準に従って、要介護の認定をするかコンピューターではじき出します。
つまりデータベース任せの判断のみで介護認定の結果を出すのは無謀でシッカリとした人の見極めが必要になるのです。例えば自分で出来ると判断されても、どこまで自分で出来るのか?トイレは自分で出来るが、お風呂は自分では出来ないと言う事はソフトには判断できませんね。
つまり介護認定を出すのはソフト(コンピューター)では無理があると言う事です。
なので、1次判定の状況をより詳しく把握し、更に調査員の調査記事および医師の意見書などを精査し介護度を決めます。
介護認定を決定する権限
認定権限は、まず医師そして歯科医師また看護師、薬剤師と介護や福祉施設の職員に全てを任されています。
一人の介護認定を決定するまでに協議される時間は平均で約1ヵ月くらいになるのです。
最終の判断結果は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階で判定されるのです。
(介護審査は総合的な物まで見られますので注意ください。例えば車いすや歩行器を借りていて無ければ困る状態など)
家庭の事情
家族全員が働いているのでなど、親は一人暮らしをしているのでなど、家庭は非常に苦しい状況なのでなど収入はまったくないのでなどなどの事情は多くありますでしょうが。
実は介護認定の時の判断材料には全くならず、完全に無視されると言う事を覚えておいてください。
ポイント
但し、非課税世帯の場合や収入が低く預貯金なども少ないなど条件に当てはまる場合↓
- 施設利用の食事代の減額
- 部屋代の減額
- 条件付き1割負担を更に減額など
- 低所得者の減額制度がある
実際には、介護度の見直しで介護区分1段階上がると、1ヶ月の保険適用額の上限金額が約5万円程度も違いますので介護区分は家族にとって大きな負担の問題となります。
・年金保険手続き目次へ行く