TOP > 家庭生活 >母子家庭の手続き > ママの手続き目次へ |
||||||||||||||
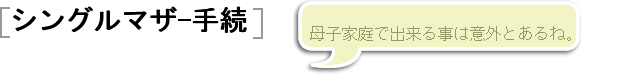 |
||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||
手続きネットよりお知らせ
皆様により分かり易く詳しく情報を提供できる有料相談お問い合わせもご用意させて貰っています。
相談窓口はTOPページ→メールサポートよりご相談ください。
 |
||||||||
|
1.児童扶養手当 |
- 母子手当と言われる児童扶養手当とは
- 離婚後の母子家庭(死別母子家庭・非婚母子家庭も含みます)が受けられる国の経済的援助(離婚後の生活をするための援助)のことです。
- 児童1人につき 全額支給 41,720円
- 一部支給 41,710円〜9,850円
- 児童2人目 5,000円加算
- 児童3人目 3,000円加算
- 児童4人目以降は、3.000円ずつ加算されます。
次のいずれかに当てはまる
- 「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母
- または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
また、児童扶養手当の金額は母子家庭の母の所得額によって変わりますので、 所得額が制限額を超えた場合は残念ながら離婚後の生活費としての児童扶養手当は支給されなくなります。
手続きネットの児童扶養手当の詳細はコチラへ⇒児童扶養手当の手続き
2.特別児童扶養手当 |
身体や精神に障害のある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し児童の福祉の増進を図るための制度です。
- 受 給 者=
身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)
- 療育手帳AまたはB1に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母
- または養育者。所得制限があります。
- 手当の月額= (平成18年4月より)
- 1級 月額50,750円
- 2級 月額33,800円
- 手当の月額= (平成18年4月より)
3.児童手当 |
児童手当法に、児童手当を使う目的が定められていますから「児童を養育するために」使ってくださいね。
- 児童手当は、第一子と第二子は5000円、第三子は10000円が支給されます。
- ただし、ここでの「第一子・第二子」というのは、支給対象になる児童のことのみを指しますので注意しましょう。
手続きネットの児童手当の詳細はコチラへ⇒児童手当の手続き
4.母子年金 |
(遺族基礎年金)
- 遺族基礎年金は、死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻、子。
- 子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことです。
- 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
- 792,100円+子の加算
- 子の加算
- 第1子・第2子 各 227,900円
- 第3子以降 各 75,900円
(遺族厚生年金)
- 遺族厚生年金は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
- 子のある妻
- 子以外に、子のない妻
- 55歳以上の夫
- 父母、祖父母(60歳から支給)
- 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者)
- または20歳未満で1・2級の障害者も対象です。
- 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
遺族厚生年金の額は、報酬比例となりますので、給料などの条件で個人差があります。
5.母子・父子家庭のための住宅手当 |
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の世帯主で
- 月額10000円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度を設けています。
助成を受けるには、各自治体での条件がありますので、それぞれのお住まいの市町村自治体の確認が必要です。
6.生活保護 |
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けをする生活に困っているときに、その程度に応じて生活保護費が支給されるのが生活保護制度です。
- 生活保護の種類として
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助の7種類があって、世帯状況を考慮した上で保護基準に従い支給されます。
平成21年度生活扶助基準額の例は、母子世帯(母親30歳、子ども4歳、2歳)は東京都区部等で157,800円。
この額に家賃等の実費相当分が給付されます。
7.片親(母子)家庭等の医療費助成制度 |
- 母子家庭等医療費助成金制度は
- 母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とします。
各自治体によって詳細は異なる場合がありますが、基本はどこも同じになります。
- 子供が18歳になった最後の3月31日まで助成制度は適応されます。
ただし生活保護を受けている人や子供が児童福祉施設等に入っている場合は助成の対象外になります。
8.小児医療費助成制度 |
- 小児医療費助成制度とは
- 0歳から中学校卒業までのお子さんをお持ちの家庭の経済的負担を軽減し、小児に対する福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
- 小学校6年生修了までのお子さんの入院及び通院、中学生以上のお子さんの入院に対する保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診・薬剤容器代・選定療養費・室料差額など)
各自治体によって詳細は異なる場合がありますので確認が必要になります。
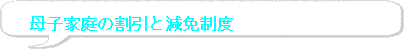 |
||||||||
母子家庭の割引と減免制度
該当する方は、職場、税務署もしくは区役所の市(課)税課におたずねください。
国民健康保険の場合>所得が基準以下の家庭、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少した場合に保険料の支払いが困難なときには、保険料を減免できる場合があります。
母子家庭・交通機関の割引についてターゲットを絞ってみましたが、その他の交通機関の割引制度を設けている所もたくさんあります。 市営バスを始め、私鉄などは直接問い合わせをしてみるのがいいでしょう。
※一部の市町村で減額免除の条件が異なっている場合や、減額免除を実施していない場合があります。 現在お住まいの上下水道問合せ窓口で相談すると良いでしょう。
普通では、預貯金の利子には、住民税として5%、所得税として15%が課税されています。
郵便局、銀行に直接お問い合わせすると良いでしょう。
ただしこの保育料の援助システムは、自治体によってかなり異なっていますので事前に確認をしましょう。
母子家庭の中でも児童扶養手当や遺族基礎年金を受けていることが条件としてあげられます。
|
||||||||
 |
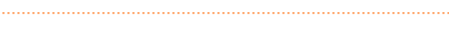 |
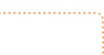 |
||||||
|
||||||||
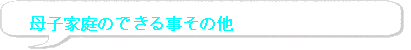 |
|||

母子家庭に出来るその他のこと
そのほかにも、母子父子で出来る事は整備されつつあります。
手当を受け取ろうとお考えであれば自分なりにもシッカリと勉強をしていかなければいけません。
また母子家庭でなくても、夫からの暴力(DV)がひどく、保護が必要と判断された場合にも入所することができます。
母子家庭や父子家庭などを対象に各自治体では、格安で最低限の生活ができるように公営住宅を提供しています。 事前に自治体に確認が必要です。
事業開始資金・事業継続資金・技能習得資金・就職支度資金・住宅資金・転宅資金・療養資金・生活資金・修学資金・就学支度資金・修業資金・結婚資金・児童扶養資金・特例児童扶養資金などの用途で適用されます。
・母子福祉資金利子補給>母子福祉資金を借りて償還している方に、3月の期間中に申請を行なえば、その年度中に支払った利子の半分を補給する制度があります。
※その他、遺族基礎年金の受取り方やシングルマザーの人気職や保育園の入園手続き方法など知りたい方は以下の手続きネットを参照してください。
|
|||
 |
||
 |
上記のような手当を貰えるにしても、母子家庭での生活は苦しいのが現状といえます。また仕事に就いている母子家庭の母親の実に49%が、臨時もしくはパート就労で、常用雇用はたったの39%。このような調査は数年おきに実施されますが、前回調査では「臨時・パート」が38%、「常用雇用」が51%でしたので母子家庭の雇用状況はかなり悪化していると言えます。
|
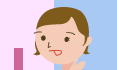 |
 |
||
あわせて読みたい記事






