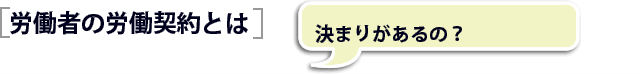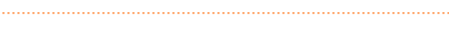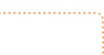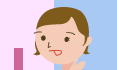つまり労働契約とは
・労働契約の概要
契約の締結の仕方や変更の仕方
- 労使の対等の立場によること
- 就業の実態に応じて、均衡を考慮すること
- 仕事と生活の調和に配慮すること
- 信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと
契約の期間
- 期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。
- なお、専門的な知識等を有する労働者との労働契約については、上限が5年とされています。
- 満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。
- 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮して貰えるのです。
契約の変更
- 労働者と使用者が合意をすれば、契約を変更できるのです。
- 合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできない。
- 使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更はできない。
- なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には
- (1)内容が合理的であること
- (2)労働者に周知させることが必要です。
労働契約の終了
- 労働者が解雇される時は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして解雇は無効となる。
- 契約期間に定めのある労働者は、やむを得ない事由がある場合以外は、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。
- 裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。
解雇予告手当
- やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うこと
- 予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要になる。
違約金や損害賠償
- 使用者は、労働者との労働契約の不履行について違約金を定めてはいけない。
- または、損害賠償を予定する契約をしてはならない。
- 違約金や損害賠償金で労働者を縛り付ける行為は禁止されています。
- また、労働者が原因で発生した損害の場合、損害について請求されます。
前借金や借金相殺
- 使用者は、労働者の前借金や、その他の前借の債権と賃金を相殺してはいけない。
- また、身内や親が使用者側から借りた借金を、子が労働報酬とその前借金を相殺する事は禁止されています。
強制貯金
- 使用者は、労働者との労働契約に付随して貯蓄や貯蓄金を管理するの契約をしてはならない。
- 労働者が任意に貯金できる福利厚生は可能です。
以上の様に、労働者と会社側には、労働する為の契約があるのです。
- つまり、この様な契約があり、労使間のトラブルや問題を事前に防ぐことが出来ます。
つまり、これから働く方や働いている会社の労働契約はシッカリと把握しておく事が重要なのです。
・仕事手続き目次へ行く