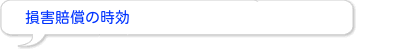TOP > 日常 > 損害賠償請求の手続き |
||||||||||||||
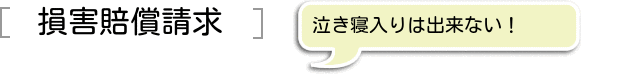 |
||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||
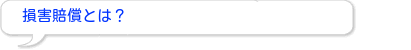 |
|
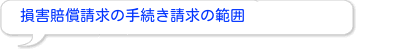 |

損害賠償請求の手続き、損害賠償請求の方法、請求の範囲について。
損害賠償請求は 違法な行為を受けて損害を被った者が、その原因を作った者に対して、損害の穴埋めを請求するものです。
損害を受けた者が、自ら手続きをする必要があります。
損害賠償請求の手続きには、大きく分けて二つの方法があります。
損害賠償請求の方法は、損害の種類や規模、当事者間の関係によって違ってきます。 それぞれの方法のメリット・デメリットを考慮した上で、各ケースに合ったふさわしい方法を選択する必要があります。 損害の種類によっては、公的紛争処理機構を利用することができます。
例えば、交通事故紛争処理センター、国民生活センター、消費者生活センターなどが挙げられます。
内容証明郵便を使って、当事者間同士で示談、合意を進める方法です。 内容証明で損害賠償請求をすると、それが証拠として採用されますので、文面には注意する必要があります。 ただ
損害賠償請求が発生する一番多いケースは、交通事故です。交通事故による損害賠償請求の場合は、双方の保険会社が間に入って交渉を進める形が多くなります。
損害賠償請求の範囲は、損害の種類によって異なります。
債務の不履行に基づく損害賠償請求の範囲は、民法第416条で定められています。 民法416条第一項では、「債務の不履行に基づく損害賠償請求は、これにより通常生ずべき損害の賠償をさせる」と規定しています。
また第2項では、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者はその損害を賠償させることができる」として、損害賠償請求の範囲を規定しています。
この条文は、不法行為における損害賠償請求の場合にも、類推適用できるというのが通説となっています。
損害賠償請求できる範囲は各ケースによって個別に判断されますが、基本として、この民法の規定が判断基準となります。
|
 |
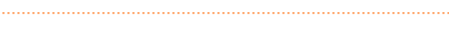 |
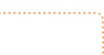 |
||||||
|
||||||||
 |
||
 |
多くの訴訟は、侵害者の利益の立証が困難な事が多く、結果的に、損害額がライセンス料として算定される。権利者の保護が十分でないという問題が指摘された。そこで、特許権、意匠権、商標権については、法改正され、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できる。これにより、損害額の立証が、容易となり、権利者の保護強化されたと。
|
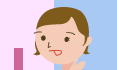 |
 |
||
あわせて読みたい記事





 交通事故における損害賠償とは?
交通事故における損害賠償とは?